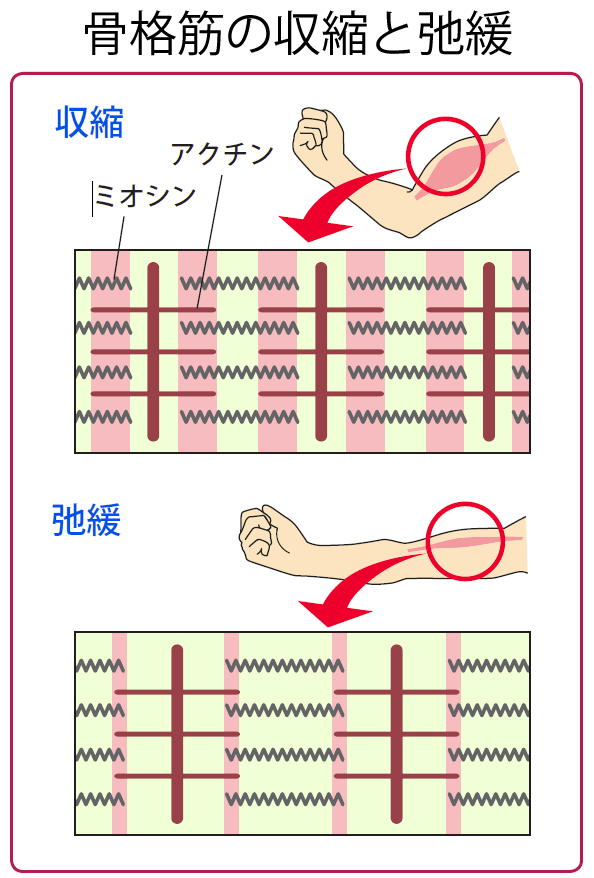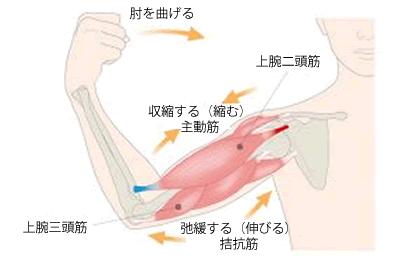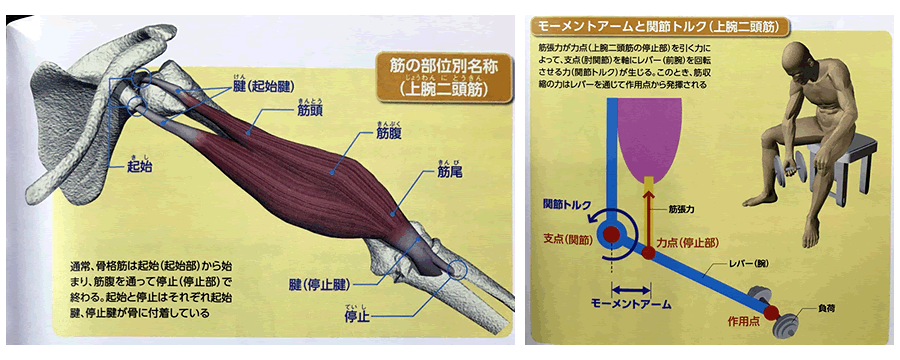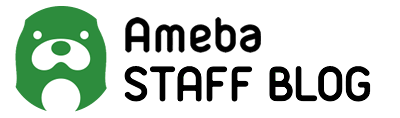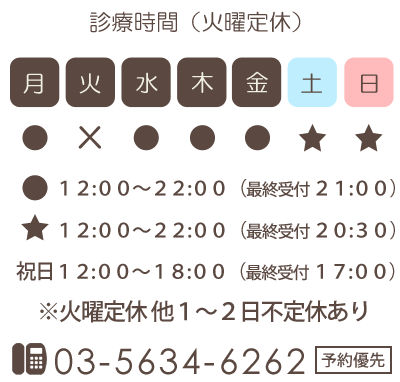姿勢と抗重力筋
図1の赤い線が重心線です。
重心線の通りに体のラインが通っていると、無駄な筋肉の緊張や力のロスがないため、一番体が疲れにくい理想的な姿勢と言われています。
左右の肩の高さ、骨盤の高さが違っていたり、重心線がくずれていたりすると無駄な筋肉の緊張や力のロスが出るため体の不調が出やすくなります。
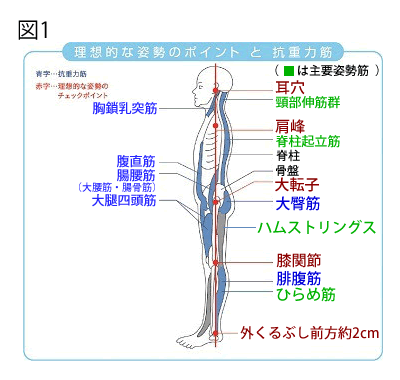
疲労と抗重力筋の仕組み
文字通り地球の重力に逆らって姿勢を保つために使う筋肉です。もともと、人は地球上では重力があって下に体が引っ張られようとしています。それを支えて、体がゆがまないよう重心のバランスをとっているのが【抗重力筋=姿勢維持筋】というもの。
運動はしていなくても、立っていたり、座るという日常の何気ない状態を維持する為にいつも使っているのが、抗重力筋ですね。
では、何故体の左右差や重心線がくずれてしまうかというと、日々同じ仕事(動作や姿勢)による疲労が大きな原因です。
その繰り返しにより筋肉、筋膜のバランスが崩れて、姿勢も崩れてしまうからです。
姿勢のバランスを崩す『疲労』には、筋肉が働き続けることで生じる疲労と、筋肉が正常に働かないことで生じる疲労があります。
この2つの疲労が負の連鎖で重なり、MRIやレントゲンでは写らない、痛みや頭痛、体の不調となってあらわれます。
同じ姿勢を続けていると、その姿勢の維持に働く一部の筋肉だけが収縮を続けて血管を圧迫するため、血行不良となって筋肉が酸欠で緊張状態になります。これが筋肉が働き続けることで生じる疲労です。
筋肉が緊張で硬くなると、静脈の血流も低下するため、筋肉中の老廃物や疲労物質が回収されずに蓄積し、筋肉はさらに疲労します。これが筋肉が正常に働かないことで生じる疲労です。
抗重力筋=姿勢維持筋と説明しましたが、その中でも特に負担がかかっている主要姿勢維持筋があります。
世の中に首、肩こり、腰痛、足のむくみが多いのも、主要姿勢維持筋が首、肩、腰、足、体の背面にあり、負担が多くかかっているため、上で説明した仕組みで疲労がたまり、体の不調となってあらわれます。
その他に、運動不足による静脈の疲労物質運搬力の低下、加齢による筋力、回復力の低下があげられます。
収縮しやすい筋肉と弱りやすい筋肉
どの医学書にも書いてあることですが、人間の筋肉は関節をまたいでいて、筋肉が収縮(縮む)することで関節を曲げたり伸ばしたりすることが出来ます。
また人の体には収縮しやすい(縮みやすい)筋肉と弱りやすい(弛緩しやすい)筋肉があり、その組み合わせが下記になります。
| 1、収縮しやすい(縮みやすい)筋肉 | 2、弱りやすい(弛緩しやすい)筋肉 | |
|---|---|---|
| 頚部伸筋群 | ⇔ | 頚部前方の屈筋群 |
| 僧帽筋上部・肩甲挙筋 | ⇔ | 広背筋 |
| 大胸筋 | ⇔ | 僧帽筋中部・下部 |
| 脊柱起立筋・梨状筋 | ⇔ | 腹筋群 |
| 腸腰筋・大腿筋膜張筋 | ⇔ | 大殿筋 |
| ハムストリングス | ⇔ | 大腿四頭筋 |
| 下腿三頭筋 | ⇔ | 下腿の背屈筋群 |
仕事で座りっぱなしだったり、立ちっぱなしの場合、いつも使われる筋肉(縮む筋肉)と使われない筋肉(弱る筋肉)が出てきます。
その結果、筋肉の収縮(縮む)と弛緩(伸びる)のバランスがくずれ、関節の曲げ伸ばしがスムーズにいかなくなり、痛みや頭痛 MRIやレントゲンには写らない、体の不調の大きな原因になります。
分かりやすい図として図1,2になります。
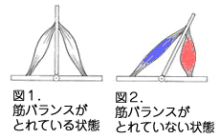
また立っている場合と座っている場合では腰への負担は、座っている方が約1,5倍の負担が腰にかかります。体が動かせない寝たきりの人の場合、2時間おきに姿勢を変えます。
そうしないと、ベッドに重く体が当たっている部分の細胞が壊死(腐ってしまうこと)して、2度と使えなくなってしまいます。
それだけ、一部の場所に負荷(ストレス)をかけることは体に悪いということです。
これを図3の足で説明しますと、長時間イスに座っていると、股関節、膝関節が曲がっています。

関節が曲がっているという事は、筋肉のバランスが崩れてしまっている状態となります。
ハムストリングス(ふとももの後面)は縮みっぱなしの筋肉に、大腿四頭筋(ふとももの前面)は伸びっぱなしの筋肉になります。
縮みっぱなしの筋肉はコリ固まり疲労が溜まります。伸びっぱなしの筋肉は筋肉が弛緩するので、力が入れづらい状態になります。
力を入れづらい状態が続くと、よりその姿勢が強調されるので、姿勢悪化が進み筋肉のバランスが崩れていきます。
筋収縮のしくみ
筋収縮は、脳や脊髄などの中枢神経から指令を受け、末梢神経が筋肉に信号を送ることで起こる。収縮するときには、太い筋フィラメント(ミオシン)が、細い筋フィラメント(アクチン)の間に深く入り込む形になる。末梢神経からの信号が途絶えると、ミオシンとアクチンの重なりは浅くなり、筋肉は弛緩する。